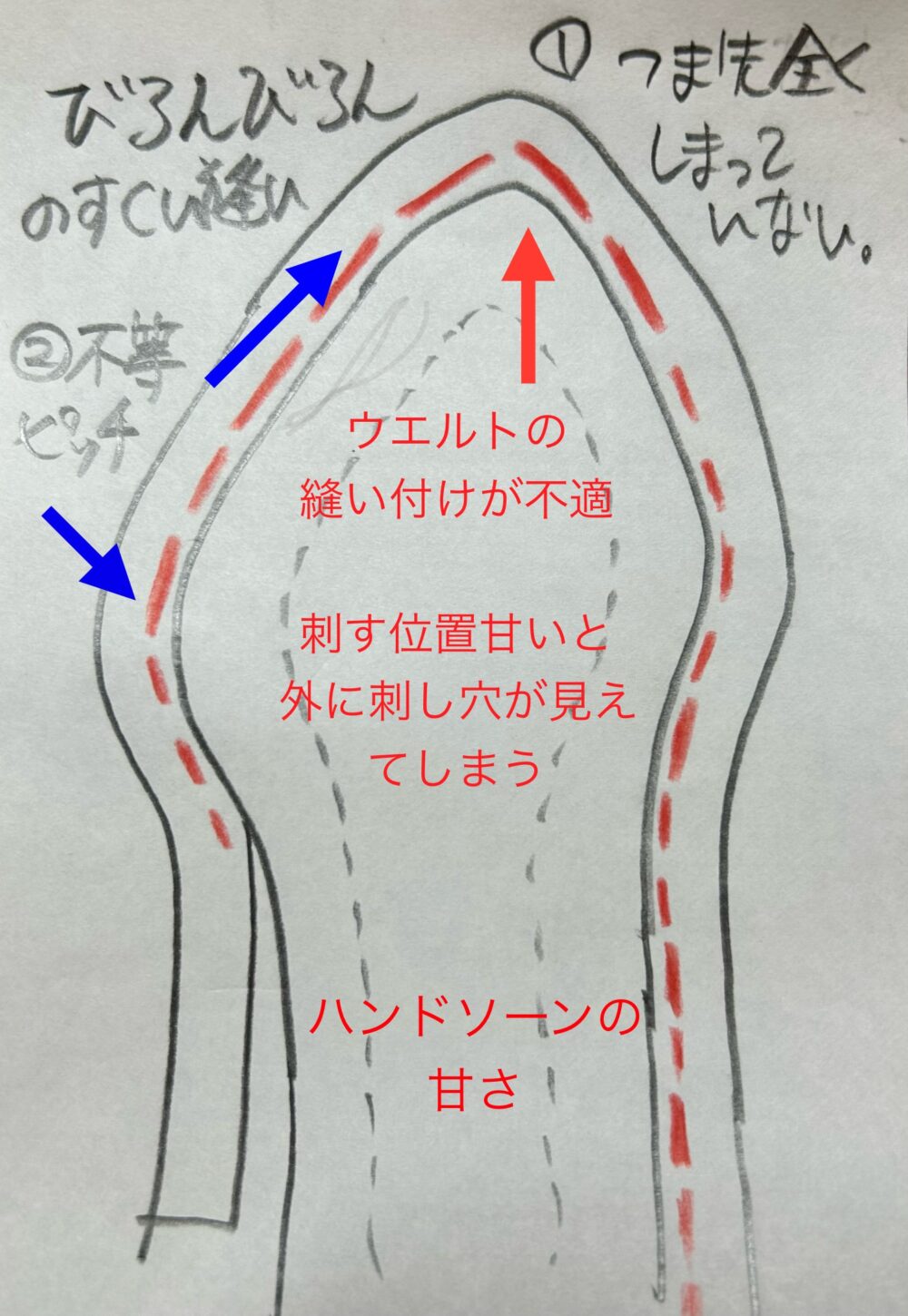前職では、毎日革靴を履いて勤務してきました。
休日も、カジュアルな革靴を履いて生活してきました。
そして、靴作りを始め、靴屋を開業に至ります。
靴を作る仕事をしているのですが、2017年に取得した「革靴製造一級技能 製甲」までは、ほとんど革靴を履くことを避けてきました。
「足に合う靴とは?」を突き詰めたい。
靴作りに悩んだとき以外は、あえて革靴を履かないようにしていました。
足の感覚を過敏にしたかったからです。
革靴を避けてきた期間、足に合わせて作る靴、履きやすい靴の研究をしてきました。
革靴を履かずに生活していると、足の動きや地面との接地の仕方、わずかな違和感にも敏感になります。
調香師が香水をつけないように、靴職人としての感覚を上げたくて、そのときそのとき自分のためになると考えられることを全てやってきたつもりです。
(フクスケの社長も、靴下履かないと言ってて安心しました。)
靴を作る中、私は「美術館に飾る壺」ではなく「毎日使うお皿」を作りたいと思っています。
つまり、眺めるための靴ではなく、生活の中で頼りになる“道具としての靴”を作りたい。
靴は、石や砂利の上を歩き、曲げられ、擦れていくもの。
一日中、人の足を支えるための道具です。
だからこそ、「履けること」「歩けること」「丈夫であること」に徹底してこだわりたいのです。
私はアートのような靴を作りたいわけではありません。
「歩くのが楽になった」「足が痛くなくなった」と喜んでもらえる靴を作りたい。
その想いで、これまでの靴作りを続けてきました。
アートの靴は、履きやすい靴作りよりもずっと難しくありません。
悩みの質は軽く、重みが違うのです。
アートは、内面からの発散、自己表現。内側を向いて作ることができる。
道具として作るには、使う人に合わせて作る必要がある。
外を向いて、外の声に応じた技術の引き出しを多く持つ必要があるからです。
「アーティスト、作家ではなく、靴屋として靴を作りたい」のです。
靴を履かなかった時期も、既製品を研究した時間も、今の自分の“靴作りの背骨”になっています。
いろいろな靴を観察すると、それぞれに思想や工夫がある。
そこから学び、次の一足に活かしていくことが、私の靴作りの原点です。
手作りだからこそできるのは、細かな微調整や、履く人に寄り添った工夫です。
しかし、「壊れない」「履きやすい」「長く使える」という基本は、精密な作りの上にしか成り立ちません。
その精度は、むしろ工業製品に学ぶべきところでもあります。
私たちが作る靴は、飾りではなく“道具”です。
履く人の動きや重心、素材の反応。
そうした小さな変化を見逃さず、感じ取ることが大切です。
「観察する目」や「感じ取る心」は、自作の靴を良くしていきます。
道具としての靴の本質に、少しずつ近づいていきましょう。